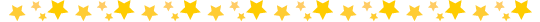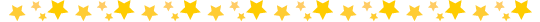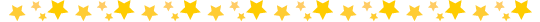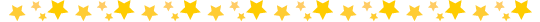|
また、ベルギーの劇作家、詩人、思想家であったモーリス=メーテルリンク によると、「もしも私がほんとうにその人を愛しているなら、私が言った言葉のあとの沈黙が、私の言葉にどれだけ深い根があるかをその人に解らせるだろう。そしてその人の心に、それもまた無言である確信を生むだろう」と。私は、せりふだけが観客にわかってもらえればそれで事が足りたと思うことは、あまりに軽薄で、本来の演技の真髄は、行間にある「なに」かをつたえられるとき「芸術の創造性の何ものか」を感じるのです。アーティストを志すならば、その点を決して忘れてはならないのです。気持ちを言葉で相手に伝える演劇は、どんなジャンルでも無意味なのです。本来人間は、話す自分と聞く相手の間には「呼吸のリズム」のような何かが存在します。それは、言葉では表現できないことですが。よく、日常でも言われる言葉に、「あいつよくしゃべるなあ、なにをいっているかわからないよ」という文句がよく聞かれますが、それはまさに、双方のリズムが合わないのです。言葉の連射は、ただ聞く相手に理解を難しくさせるだけではなく、嫌悪感も相手に植えつける結果になってしまうのです。また、「愛のささやき」には、愛の告白とともに間隙も必要なのです。とどのつまりは、「人間での感情表現に間隙の要素が必要不可欠です。但し、ここで忘れてはならないことは、「間隙」ととも「しぐさ」が伴うとより相手にわからせることができます。つまり、「非言語の世界」の助けを借りることです。「しぐさ」について、千田先生は、俳優の芸術は決して一人ではできない、他の人々(その他の俳優たち・作家・演出家)と一体になって成り立ち、また見物人たちも俳優の身振り・言葉の形からその意味を読み取り感じると同時にいろいろの関係(人と人、人と物、人とそのおかれた場面との関係)を読み分ける感じ取る感覚を身につけていなければならないといっています。ところで、私はここで述べたいのは、日本の演劇が国際的になりにくい根拠の存在を認識するのです。日本という特殊な国では、ほとんどが同じ種族の単一民族ですので、見物人もある程度の役者の動作の「間隙(沈黙)・しぐさ」からある程度、そのときそのときの役者の感情と同化しやすく理解が容易であると思うのです。喜怒哀楽の同一性が双方に認められるのです。ところが、外国でそのままの場面を演じれば、大いに支障が生じて、最悪の場合、嫌悪感を感じてしまうことになりかねないかと懸念します。「非言語の世界の研究」が日本の演劇界ではほとんどされていないのが現状です。その分野の専門家であるバードウィステルの研究によれば、対人コミュニケーションで言葉が占める割合は、30%ぐらいで、残りは、非言語の割合で70%ぐらいだそうです。いかに非言語の世界が重要かがわかります。この世界の研究を通じて「誤解」を乗り越えなければ、日本の「演劇」は、年に何回かは、「日本の伝統の歌舞伎等」は海外公演されていますが、「日本で作られた一般の演劇」が、海外で上演され人気を博しているとついぞ聞いたことがありません。逆に「海外の演劇作品」を日本人向けに再構築して公演することはよくありますが。本当の意味で日本の一般的な演劇」が国際舞台で上演されるには、はるか未来にならないと実現しないように思われます。1578年、日本での布教方針を考えるにあたり、イエズス会東インド巡察師アレシャンドロ=ヴァリニャーノは、「日本人は喜怒哀楽を表情に出さないので、いったい何を考えているのか自分たちヨーロッパ人にはさっぱりわからない」と述べています。
|