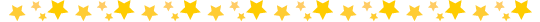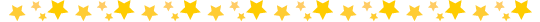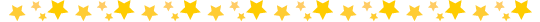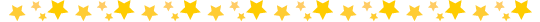|
そして、私は、宗教と芸術(音楽)とに間に関連性を感じるのが、教会とパイプ=オルガンの並存なのです。ここで芸術の一形態の音楽に焦点を絞って話を進めようと思います。音楽でも一般に知らせれいているジャンルとは違うまさにマージナルな(辺境的・社会の範疇にはない)もの、すなわちロム(rom)音楽を考えてみたいと思います。たぶん多くの方は、『それは何ですか?』と質問すると思いますので少しロムから説明しますと、一般に定住社会圏を持たない『放浪の民』といわれ昔から世界中を旅した民であります。ドイツ語ではZigeunerといわれているが、彼らの生活は歌い踊り、手相占いをしていました。ここで注目されるのは、かれらは、野や森や川つまり大自然を愛し、自分らを『自然の王』という。以上の理由から彼らが歴史上登場することは皆無に近く彼らにつての資料を入手するのは大変難しいのです。現在では、彼らの系統をひくスペインでのGitano(ヒターノ)に見ることができます。特にかれらは、音楽分野で才能を発揮して『フラメンコ音楽』を紹介してきました。少し、フラメンコのついて説明しますと(私自身もフラメンコギターを勉強していましたが)、スペイン南部アンダルシアのヒターノの間で19世紀半ばに生まれました。これに、フェニキア人、アラビア人、ユダヤ人の芸能とミックスされたものといわれでいます。カンテ(歌)、バイレ(踊り)、ギターラ、サパテアード(足拍子),パルマーダ(手拍子)、12拍のリズムによって構成されています。フラメンコのリズムは、十数種類があり:神秘的なソレア・陽気なアレグリーアス・ブレリア・タンゴス・ティエントス・不思議な感じのシギリージャス・ファンダンゴス・マラゲーニア・ベルディアレス・グラナイーナス・タラントs・タンゴ=デ=マラガ・ファルーカ・ガロティン・ペテネーラス・セビジャーナ・グァヒーラス・ルンバスなどがあります。ここで忘れてはならないことは、フラメンコの仲間の間では、「Duende」の存在を信じています。それは、霊であり妖怪でありその力によって舞台が展開しているといわれています。フラメンコの話が長すぎたので話をその流浪の民へ話を戻すと、この章でのもうひとつのテーマである宗教に関連した疑問として、『彼らには、宗教があるのか』ということを考えてみたいと思います。、キリスト教徒に言わせれば、宗教に縁のない民であると。私は、むしろある枠に囚われない教義を持たない、ある種の自然崇拝(アニミズム)であると思われます。別の章で述べましたケルト民族やゲルマン民族との共通点が感じられます。共通点の考察を試みてみたいのでが、別の機会に譲るとして、とにかく、流浪の民は森の精や川の精・太陽・星・この宇宙全体を信仰しています。ここで、この民の迫害の歴史を紹介したいと思います。彼らのヨーロッパでの出現は、15世紀の始めといわれています。何故15世紀からの登場かといえば、中世の終焉の時期で、都市の発展・貨幣経済の活発化・商業の発展の地域的広がり・利潤の追求等が見られ物的なのみならず人的な交流も活発化したのです。そのような状況で、彼らがヨーロッパと接することが可能であったと私は思うのです。残念ながら、gadscho(軽蔑的な意味を込めたヨーロッパ人への呼び名)社会では、乞食・最下層民として位置づけれ、それはまさにユダヤ人と同じでありました。彼ら流浪の民は、歴史上には載ることがなくその意味でヨダヤ人より悲しい存在でした。最近の例としては、ナチスの迫害があります。ユダヤ人迫害としては、よく知られていますが、その蔭に(彼らの居場所)彼らがいました
|