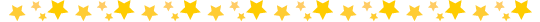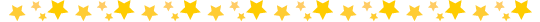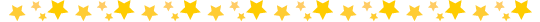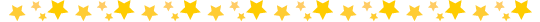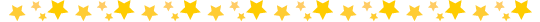
 |
Die Fortsetzung |
|
次に『芸術の存在意義』について考えてみたいと思います。ご存知のように、現在という時代に目を向ければ、科学・技術の進歩による恩恵を多くわれわれは受けています。例えば、医学の進歩による寿命の伸長、水力発電による電気の供給、天気予報のある程度の予測、安定した食料の生産、交通機関による時間の短縮化それに伴う流通産業の効率化、コンピューターの普及による情報の迅速化、別の見方をすれば戦争武器の破壊力(科学兵器・核兵器)の未曾有の進歩その他例を挙げればいくらでもあるように科学・技術の偉大さには賞賛を惜しみません。しかしながら、何か物質的な面だけが先行している傾向があるように思われてなりません。『こころの貧困化』とよく言われます。現象として敵対心・猜疑心(不信)・命の軽視・他人に対する思いやり・ものに対する愛着心の軽薄・自然に対する畏敬の念の欠乏とその破壊・日本における自殺者の増大・人間同士の殺し合い・戦争・虐殺その他。なぜこのような不均衡が生まれたのでしょうか。人間は、新しいもの・便利さ・合理性を好む傾向が先天的にあり、それらに魅了されてしまうのです。それの飽くなき追求により人間は『何か大きなもの』を置き去りにして邁進しているように思われます。人間の弱さといえばそれまでの話ですが、そのような状況に『芸術の果たす役割とは何か』といつも考えるのです。小説、悲喜劇、絵画、彫刻、舞踊、建築等がいわゆる芸術といわれる分野ですが、それらの果たすべき役割とは甚大であると思われます。それらは人間の内面性を追求したものであり、社会に与える影響を考えると責任重大であります。ロシアの文豪トルストイは、次のように『芸術』を定義しています。『個人を人類の生活にとっても善に向かう運動にとってもなくてはならない必要な人間の交通手段、人間を同じ心持の中に結びつけるための手段である』。その言葉の中にすべてが言い尽くされていると思うのです。同じ心持を生まれださせるのが芸術の使命と、また芸術のテーマがいつも真剣に問われなければならないと思うのです。ところで、私がこの芸術論(1)で述べた『芸術は、文明にLuxを放射し文化に虹彩を与えるものである』と述べましたが、最近読んでいますトルストイの『芸術とは何か』で別の見方が論述されていますのでご紹介したいと思いますーー苦しみ、快感を実際または想像で味わった人がカンバスや大理石に表わしたものを見て、他の人たちがそれに感染した場合それがまさに芸術である』と。そのような観点では、絵画も石教会堂の建築物やそれに彫られた諸聖人像は、芸術作品と言えるのではないでしょうか?彼は言葉を続けます『見る人聴く人が創作家の受けた心持に感染すると、それで芸術になる。もし人間に、昔生きていた人たちの頭に浮かんだ思想を(言葉)で現したものを取り上げたり自分の思想を他の人に伝えたりする力がなかったとすれば、人間は野獣と同じである、また人間のもうひとつの力、(感情の領分の芸術)によって感染する力がなかったならば、人間はもっと野蛮なもの、最悪の状況としてこの人間界は、無秩序で敵同士になっていたかも知れないのです』と。つまりここで、私の理解としてある意味で『芸術は文化の諸形態に虹彩を放射するフォース』であり、人類の永続、平和維持にはなくてはならないものなのです。
ラテンの言葉:Ommes artes,quae ad humanitatem pertinent,habent quoddam commune vinculum.(人間性に関わるすべての芸術は、ある共通の絆を持っている) |
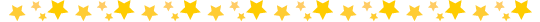 |