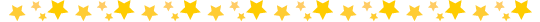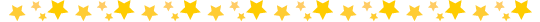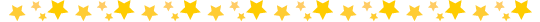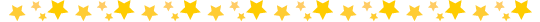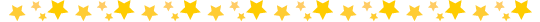
 |
Die Einleitung |
|
最近私は、『演技』について考える場合、まず第一に考察しなければならないことは『文化』とは何かということです。社会科学的見地からは、『文化とは何世代にもわたる個人や集団の努力によって多くの人々により受け継がれた知識・経験・信念・価値観・態度・意味・階級・宗教・時間の観念・役割分担・空間の使い方・世界観・物質的な財産などすべてを包含したものである。』と。この解釈を通じて、わたしの見解として、人間社会が存在する限り、換言すれば一人の人間では『文化』は生まれにくいものであり、自分以外の他者が存在しなければ成り立つのが困難である。但し、それは明確な概念ではなく、まるでオブラートそのものであるように思われる。つまり、先ほど述べた知識やその他の諸概念を包含する透明可視的なものであり、次の世代がその中を見通して学ぶものである。また、『文化』は、ある種の生き物のように感じられる。つまり、アメーバーでありその時代、また別の時代に外見的に変身しながら存在し続けるのである。いづれにしても、『文化』という器に先ほど述べた諸概念が存在している。『芸術』も然りである。しかしながら、芸術の存在意義は、『常に新しいものを作り上げる創造的なものであり,実在表現のLux(光)を放射し続け文化に虹彩を与えるもの』であると確信します。
私の専門分野のひとつである『西欧の教会建築、イコノグラフィー(図像学)』では、西欧の12世紀以前のロマネスク様式と12世紀以降のゴシック様式とは、別物に見られる傾向があるが、私は、前者が存在したから後者が生まれたと思われます。つまり、文化の性癖である『過去から学ぶ連続性』を痛感せずにはいられないのです。フランスのラン大聖堂、アミアン大聖堂、シャルトル大聖堂等のそれらの建築物は勿論のことそれらに付帯した壁面に彫られたイエスの姿や諸聖人の人物像またマリア像などの彫刻作品は、『宗教的信仰の対象物としての宗教的作品』という本来の価値を認識する以上に『崇高な芸術品』としての価値をそれらに見出すのであります。
『芸術』の別の視点として、本来は、それは自己表現の顕在化であり、自己の感情の発露である。その点では、『芸術』という言葉では、本質的な意味では偏狭的な理解に陥ってしまうのであり、その言葉では包含することができないものであります。例えば、西欧の中世に隆盛しました『巡礼』という行為現象を考えてみても、人間は、そのときはひとつの明確な『信仰心』といわれる動機がその行為に導いたことは確かでありますが、中庸的な見方をすれば、『自己感情の表現行為』ということも言えるのではないでしょうか?また、現在、アフリカやその他の文明社会から犯されていない社会圏でのいろいろな集団儀式を執り行うときに付帯的要素として『踊り、衣装、化粧』の行為が、まさに『自己表現の顕在化』であり、自己存在の確認を意識することであります。
話は芸術の『常に新しい創造性の追及』に戻ると、模倣的・クリシェなものは排除される。つまり、現代という時間の中で所謂「古典」といわれる芸能(日本でいえばー能・浄瑠璃・歌舞等)が伝統に完全に100%制約されたものであるならば、形骸化され一般の人々からの関心事から取り残される運命にあります。常に、その時代に適合するように努力し新しい要素の構築しなければならない。諺曰く”The rolling stone gathers no moss.":つまり、流転しているものは、苔が付かない。
スタニスラフスキイの言葉を借用させていただくならば『創造的芸術』の追及であります。 |
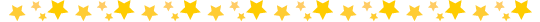 |